一力遼棋聖「学習と囲碁」を語る
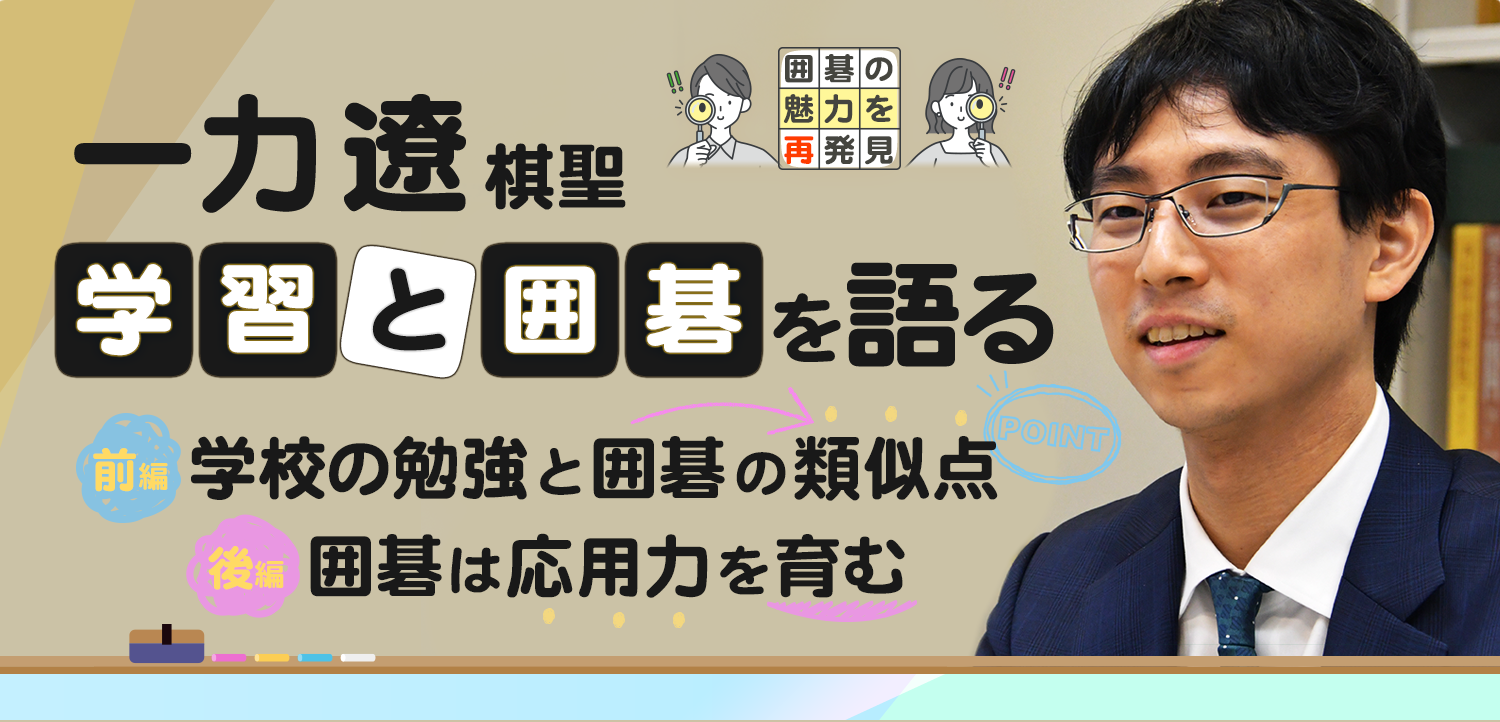
KUMONは「囲碁」の普及を応援しています
※文化庁の「令和6年度生活文化創造・戦略展開事業」に公文囲碁を入口とした囲碁の各種普及事業が採択され、
公文エルアイエルは囲碁の普及に取り組んでいます。
日本の伝統文化で頭脳スポーツの囲碁は、かつて庶民の間で広く親しまれ、財界、政界でも欠かせないコミュニケーションツールとなっていました。当時の囲碁のプレゼンスを鑑みて、KUMONは1985年に「公文囲碁」をスタート。その後、事業を一時停止していましたが、KUMONグループの公文エルアイエルがパンダネットと「公文囲碁」に関するライセンス契約を結び共同事業として、2024年10月に囲碁入門者に向けたオンライン学習の形で「公文囲碁学習サービス」としてスタートしました。
4000年の歴史を持ち、日本で文化として発展し、世界中(国際囲碁連盟の加盟国・地域は、79カ国・地域)にプレーヤーがいる囲碁。もう一度人々の間で普通に親しまれる娯楽にしていくには何が必要なのか。魅力を再発見し普及に繋げていくために、様々な方にお話を聞いていくことにしました。
今回お話を伺うのは日本囲碁界の第一人者である一力遼さん。現在日本の7大タイトルのうち4冠を保持し、昨年には19年ぶりに日本勢の世界戦優勝をもたらし脚光を浴びました。まさに世界を股にかけて活躍するトップランナーです。
一力さんは中学生から棋士として活動されています。それだけ聞くときっと囲碁漬けの生活をおくっていらしたに違いないと思う方も多いと思いますが、実は高校(都立白鴎高校)、大学(早稲田大学社会学部)と進学し、現在は家業である新聞社(河北新報社)で経営に携わる会社役員でもあります。
囲碁に専心する傍らで学業もこなしてきた一力さんはどのように勉強をしてきたのでしょうか。「学習と囲碁」をテーマに一力流学びの秘訣に迫りました。(インタビュア = 品田渓 / 記事の内容は2025年1月掲載当時)
一力遼 棋聖・名人・天元・本因坊
1997年(平成9年)6月10日生。宮城県出身。宋光復九段門下。2010年入段、20年九段。13年第8回広島アルミ杯(~通算2期)、14年第39期新人王、第1回グロービス杯世界囲碁U-20優勝、第39期棋聖リーグ入り(16歳9ヵ月でのリーグ入りは史上最年少記録)。16年第25期竜星(~通算4期)。17年第65期王座戦挑戦者(~2期連続)、18年第25期阿含・桐山杯(~通算3期)。19年プロ棋士ペア碁選手権2019優勝、第66回NHK杯優勝(~通算4期)。20年第45期碁聖、第46期天元(~通算3期)。22年第46期棋聖(~3連覇)、23年第78期本因坊(~2連覇)、第19回アジア競技大会男子団体戦銅メダル。24年第10回応氏杯世界選手権優勝、第49期名人。
【前編】 学校の勉強と囲碁の類似点

KUMONは 「学習」をサポートする事業を行っているので、一力さんがどのように囲碁や学校の勉強を学習されてきたのかぜひ知りたいです。まず囲碁ですが、一体何をしたらそれほど強くなれるのでしょうか。
一力さん)特別なことはしていないと思います。子どもの頃は詰碁(練習問題)と棋譜並べ(上手[うわて]の対局を勉強すること)をし、教室などで同じくらいの相手とたくさん対局しました。現在でも詰碁、棋譜並べ、対局といった基本は変わっていません。変わったところはAI研究を行うようになったところと、直近に控えている対局に合わせて勉強内容をカスタムするようになったところでしょうか。
特別なことをしていないけれどそこまで強くなられたということは、やはりものすごい量をやってらっしゃったのでしょうか。
一力さん)子どもの頃は勝ってレベルアップするのが楽しくて四六時中やっていました。今もそれはあんまり変わっていないかもしれませんね。
囲碁に熱中していたとはいえ、学校の勉強もしていたのですよね。素朴な疑問なのですが、一力さんはどんな小学生だったのでしょうか。親御さんから「勉強しなさい」と言われたことはありますか?
一力さん)4、5歳の頃から数字と算数が好きでした。小学校で覚えているのは当時の校長が数学好きだったのか、校長室の前に算数の問題が張り出されていたんですよね。パズル的な面白い問題が多くて、そこの問題を解くのを楽しみにしていました。両親から勉強するように言われた記憶はありません。だいたい宿題は学校の休み時間に終わらせていました。
一力さんの数字好きは伺ったことがあります。3桁の素因数分解が即座にできたり、生年月日を言うとその日が何曜日か当てられたりするそうですね。
一力さん)そうですね。子どもの頃からそういうのは得意でした。
算数では困ることがないですね。逆に苦手な科目はありましたか?
一力さん)昔は作文が苦手でした。漠然として答えがないのが難しかったのだと思います。大学で小論文を書いたり、記者として記事を書いたりする中でだんだん苦手意識はなくなっていきました。
お話を伺っていると、囲碁にしても、学校の教科にしても、ごく自然に勉強されているように感じます。
一力さん)対局では集中力が不可欠です。局後は対局のどこが良くてどこが良くなかったのかフィードバックをし、足りない部分を見つけてどうすればそれを克服できるのかアプローチを考えます。集中力と適切なフィードバックと課題に向けたアプローチ、これらは勉強全体に当てはまることです。
学校の勉強にも囲碁で培った方法論を応用できるということですね。
一力さん)自分の中で達成度を数値化し、課題を1つ1つクリアしていく感覚は同じですね。例えば私は詰碁を毎日1問1分と時間制限を設けて30問程度解いているのですが、試験勉強も漫然とするよりも時間制限を設けて理解度を測る方が、効率がいいように思います。また、対局が控えている場合はだいたい2週間前くらいから対戦相手の研究を行って、どういう布石(最初の打ち方)にするかを決めます。試験前も2週間前くらいから過去問などで傾向と対策を立てて本番に挑むので、似ている部分は大きいと思います。
KUMONは、 時間を計って教材を学習することで、一人ひとりにあった「ちょうどの学習」を追求しています。一力さんのお話を伺って、KUMONの考え方とつながっていらっしゃると感じました。 棋士として活躍する中で大学まで進学されましたが、大学に行って良かったなと思うことはありますか。
一力さん)在学中はタイトル戦と授業に課題で単純に忙しく、良さを実感する余裕がありませんでした。ですが、卒業してから良かったなと思うことはあります。特に大学に行ったことで人とのつながりができたのは財産だと感じます。早大は卒業生が多いので、あちらこちらで「私も早稲田なんだよ」と声をかけていただき、ご縁がつながることが多いです。
【後編】 囲碁は「応用力」を育む
日本囲碁界の第一人者、一力遼さんに「学習と囲碁」をテーマにお話を聞いています。後編は一力さんを捉えて離さない囲碁の魅力と普及への想いを伺いました。

今改めて振り返って、囲碁の何に惹かれてのめり込んだのだと思われますか。
一力さん)前編でも少し触れましたが、最初は特に「勝ってステップアップしていく」ということが楽しかったのだと思います。また、私はその時々でいい指導者に恵まれました。囲碁のゲーム性でいうと、定石化されている部分が少なく未知の部分が多いというところにハマったのだと思います。
囲碁人口は年々減少しています。他にもたくさんの娯楽がある中で囲碁を選んでもらうために、一力さんがPRしたい囲碁の魅力は何でしょうか。
一力さん)まず私自身、囲碁はとても奥が深くて面白いものだと思っています。囲碁ファンの方も総じて熱量が高い方が多いです。ハマるとハマるのが囲碁なのだと思います。ハマる大きな理由はルールがシンプルで自由度が高いところにあると思います。また、勝ち負けの幅が半目(最小差)から100目以上の大差まで大きいというのも囲碁ならではです。100 ー 0 ではなく、60 ー 40 もありえる、どこかで損をしてもその損を上回る得をすれば良いというような俯瞰的な判断が求められます。
経営者などに囲碁ファンが多いのもそのためでしょうか。
一力さん)そう思います。先ほどシンプルで自由度が高いと言いましたが、特に人と人との対戦では自分がどんなに定石通りに打っていてもどこかで必ず定石を外れます。囲碁は未知の局面での対応力、経験やヨミを駆使した応用力を求められるという点でも魅力的です。
どういう方に囲碁をやってほしいと思いますか。
一力さん)全世代の方におすすめですが、特にお子さんや学生の方など、若い世代の方にやってほしいと思います。囲碁に打ち込むことで集中力や総合的な判断力、応用力が育まれますし、それは社会に出た後にも役立ちます。あと、個人的に重要だと思うのは負けた時にどうするかです。
負けた時ですか。
一力さん)囲碁は必ず勝敗が付きます。当然負けることもあるわけですが、その時に相手を認め、自分の手を反省すると成長につながります。最近は教育現場で勝ち負けをつけないことが多いと聞きますが、人生の中で競争は避けて通れません。負ける経験がないまま明白な結果が出るものにぶち当たるとメンタル的に大変なのではないかと思います。
囲碁で「負けること」を経験しておくと、別の場面で上手くいかない時も気持ちを切り替えて前に進んでいけそうですね。たくさんの良さがある囲碁ですが、普及については思うように進んでいるとは言えない状況です。囲碁を新たに学びたいと思う方にとって障壁になっているのは何だと思われますか。
一力さん)これはコインの表と裏のようなものなのですが、囲碁はルールがシンプルで自由度が高い一方で、初心者の方にとっては目的が漠然としていて難しく感じるという側面があります。
入門の現場でよく「ルールは簡単でも打てるようになるまでが難しい」と聞きます。
一力さん)碁盤が広過ぎて、着手が自由過ぎて、初心者の方が何をしていいのか分からないんです。その状態を乗り越えて自分で打てるようになるとすごく面白くなるのですが、そこに至までに挫折してしまう方が多いのは事実です。
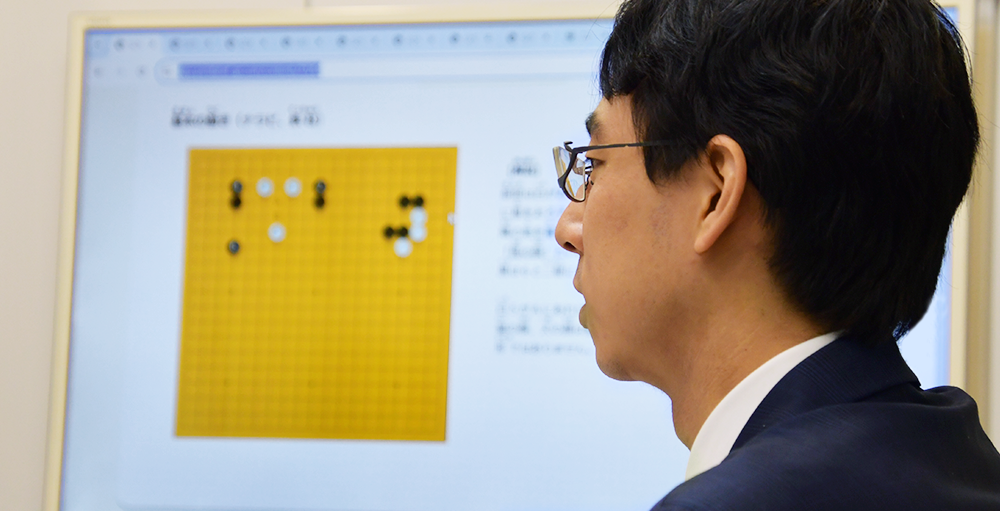
今回デジタル化した「公文囲碁」はまさにルールを覚えた方が自力で打てるようになるまでのサポートを目指したプログラムです。
一力さん)拝見しました。ここまで体系だった入門者向けの学習プログラムは今までなかったのではないかと思います。パンダのキャラクターやメダルを集めるといったゲーム性が盛り込まれて、小さいお子さんでも楽しくできそうですね。
最後にこれから囲碁をはじめようかと考えている方に一言お願いします。
一力さん)囲碁は非常に面白いゲームです。年齢、性別、国籍関係なく一生楽しめますし、判断力や応用力も身に付きます。ぜひお近くの囲碁教室に行ったり、「公文囲碁」などの入門プログラムを活用したりして、はじめてみていただきたいです。そして、最初は難しく感じても後からどんどん楽しくなってきますので、安心して続けてほしいと思います。

◆ ◇ ◆
◆ “公文囲碁”で基礎を学習「パンダネット囲碁入門」

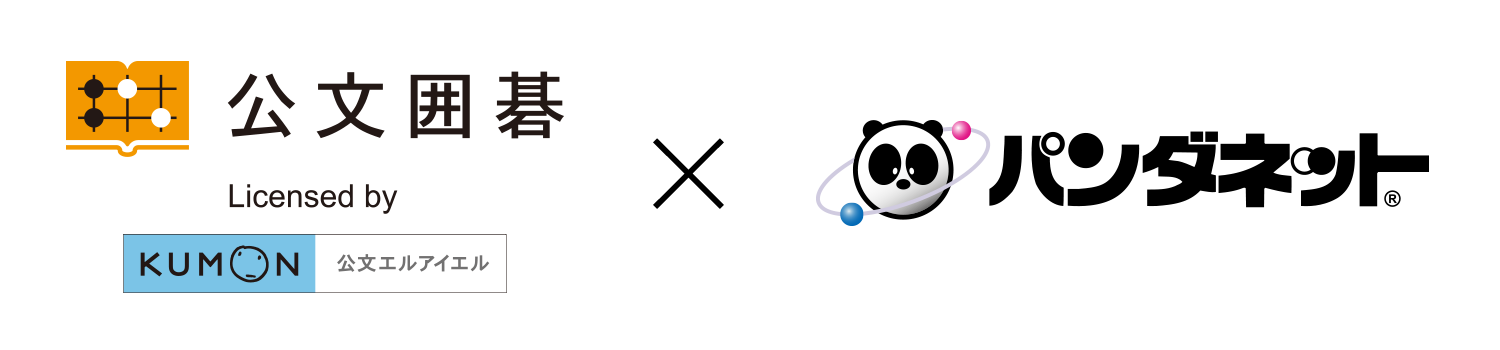
“公文囲碁”による基礎学習と、パンダネットの囲碁AIロボットとの実戦対局を組み合わせた、「学習」と「実戦」のサイクルが組まれた、これまでにない囲碁入門者に向けたサービスです。詳しくはオフィシャルホームページをご覧ください。
パンダネット囲碁入門のホームページへ





